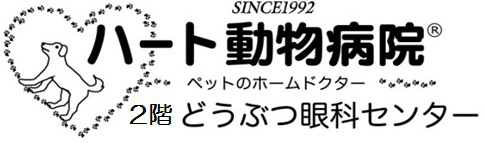~黄疸のお話~
黄疸とは血清ビリルビン濃度の上昇によって起こります。重度の場合は白目や歯肉、皮膚などが黄色くなることがあります。

今回はこの黄疸について少しお話しします。
【はじめに】

黄疸は血液の病気や肝臓、胆道系などの病気で起こります。ビリルビンの約70%は老朽化した赤血球のヘモグロビンに由来し、残りは骨髄やヘム酵素などに由来します。
血清ビリルビン濃度は
ヘモタンパク質の放出 → 肝細胞における取り込み → 抱合 → 胆汁中への排泄のバランス
を反映しています。
【ビリルビンの流れ】
1、ビリルビンの生成
赤血球のヘモグロビンが分解され、最終的に間接型ビリルビンが生成されます。
2、肝細胞への取り込みと抱合
肝臓に運ばれたビリルビンは肝細胞内に取り込まれまれ、直接型ビリルビンに抱合されます。
3、排泄
ほとんどのビリルビンが胆汁中に排泄されます。胆汁は胆嚢の収縮により消化管内に入り、一部は再吸収されますが、最終的に糞便中に排泄されます。

【黄疸の種類】
血清ビリルビン濃度が上昇した場合、病態により3つに大別することができます。
肝前性黄疸
肝臓自体には異常はありませんが、肝臓の処理能力を上回るほどの大量のビリルビンが負荷された時に起こります。
例)溶血性貧血、など

溶血性貧血

脾臓での破壊亢進
肝性黄疸
肝臓内の胆汁の鬱滞、肝細胞の機能が低下した場合に起こります。肝細胞の機能低下により、ビリルビンの取り込み、抱合、輸送、排泄の各段階が障害されることによります。
例)肝炎、肝硬変、薬物、など
肝後性黄疸
肝臓から排泄された胆汁が、何らかの理由で閉塞することにより、鬱滞することで生じます。
例)胆嚢粘液嚢腫、炎症、腫瘍、結石、など

黄疸は様々な病気で生じます。動物の場合、全身が毛に覆われているため、わかりづらいです。白目や歯茎、皮膚の薄い部分(お腹や耳など)で確認すると比較的わかりやすいです。また、尿の色などでも見つかることがあります。
しかし、目で見て「黄疸だ!」とわかるくらいだと、重症であることがほとんどです。「元気ないな」「最近、食欲がない」「よく吐いてる」など、異常を感じた時点で先生に相談しましょう!